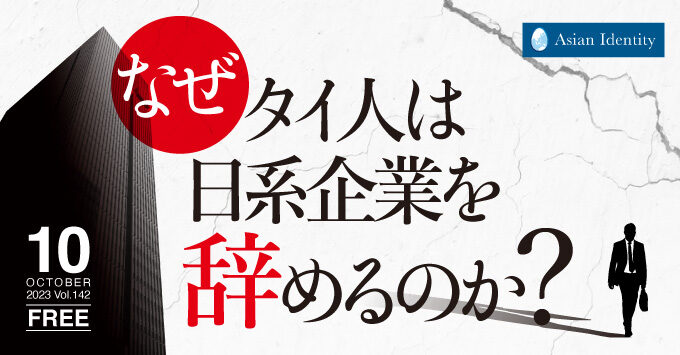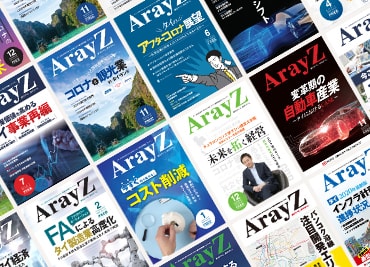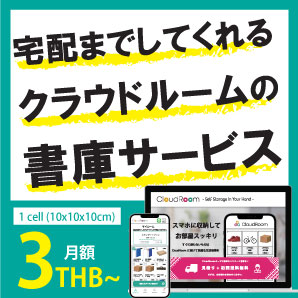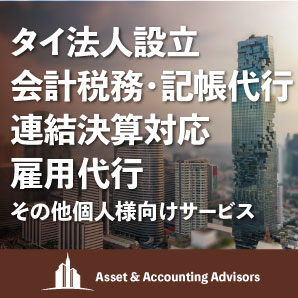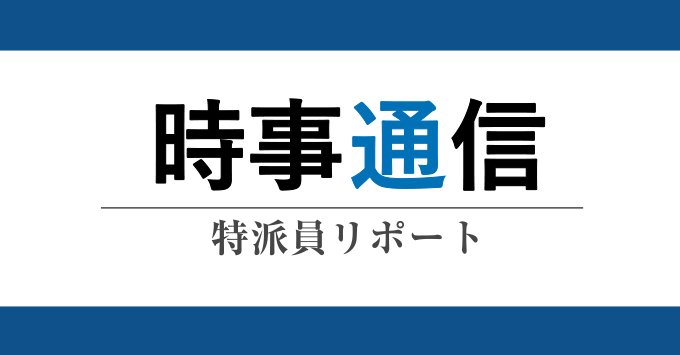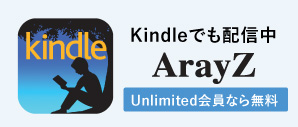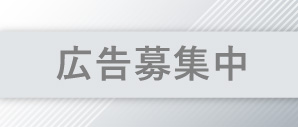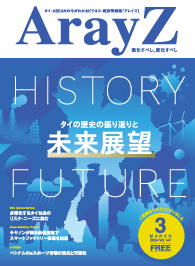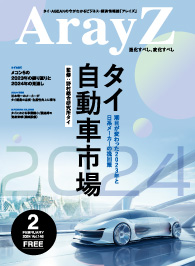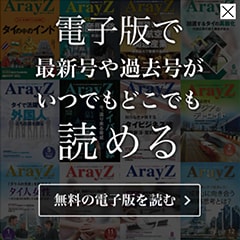カンボジア自動車産業のこれから

- この記事の掲載号をPDFでダウンロード
メールアドレスを入力後、ダウンロードボタンをクリックください。
PDFのリンクを送信いたします。
カンボジアでは新車販売の割合は極端に少なく、市中で走る自動車のほとんどは海外からの輸入中古車だ。ASEANの中でも、このカンボジアの自動車市場は特殊な状況にある。
だが、その現況からの変化がいよいよ訪れるとも言われている。そのシナリオについて、全く異なる二つの可能性を論じたい。
これまでのカンボジア自動車市場

プノンペン市内の独立記念碑前を走る輸入車(2015年)
まずは、カンボジアの自動車市場について少しおさらいをしておく。
カンボジアは自動車製造という観点では、独立したエコシステムは形成されていない。カンボジアはタイ+1(プラスワン)の位置付けと言ってもいい。
タイの自動車サプライチェーンが染み出すかたちで、特にタイと隣接したポイペト等に一部の製造工程が移管された。車両組立工場はないため、カンボジアで走っている車は他国から輸入されたものになる。
その輸入関税は新車、中古車ともに非常に高い率が掛けられている。そのため新車ではなく、事故車同様の安価な中古車を低い関税額で輸入し、カンボジアでリペアして流通させるというやり方が定着している。
なお、カンボジアで整備・修理のインフラが整っているわけではない。そのため、カンボジアでのリペアにおいても、熟練度の低い修理工が偽装パーツを使って行っているという状況だ。
また、そもそも正規の輸入ルートを通さず、グレーマーケットを使って非課税で入ってくる、より質の低い車両も多く存在する。
このように、これまでのカンボジア自動車市場は、一般的な自動車エコシステムが機能している状況には程遠い段階にあった。だが、その状況は少しずつ変わりつつある。
仮説① 従来型の自動車バリューチェーン形成
モータリゼーションが進むと言われている一人あたりGDP3000USDのラインは、既にプノンペンでは超えたと言われている。そうなってくると、消費者購買力の観点から、カンボジア自動車サプライチェーンの在り方も変化を促されるだろう。
実際、今年3月から自動車輸入関税が大幅に引き下げとなった。これはコロナ禍による購買活性化策の一環という側面もある。
だが、本質的には、カンボジアとして自動車バリューチェーンの正常化にいよいよ本腰を入れることの表れとも聞く。当然ながらその背景には、消費者側の購買力・購買意欲が閾値に達したという点があるのだろう。
もちろん、自動車バリューチェーンの形成に向けて整えなければならないものは、車両自体の安全規制や中古車そのものの規制など他にも多い。
しかし、消費者側の変化と制度の整備は前に進んでいくことは間違いない。その時間軸には議論の余地があるが、カンボジアでも順当に自動車バリューチェーンが形成されていくだろう。
仮説② 自動車〝利活用〟社会へのリープフロッグ
以上がベースラインとしてのシナリオだとすれば、それとは全く別の進化を遂げていくというシナリオもあり得る。それが自動車〝利活用〟社会へのリープフロッグだ。
現在、先進諸国をはじめとして世界では自動車の保有ではなく、シェアリングというかたちでの自動車社会の形成が模索されている。
ここASEANでもGrabやGojekといったライドヘイリングはもはやその枠を超えて、食品デリバリー等の日常生活に深く入り込んでいる。
カンボジアにおいてもGrabは進出済みである他、PassAPPなどのローカル勢も多い。また、伝統的な自動車利活用手段であるレンタカー市場も活況で、Avis等のグローバル大手も参入している。これら自動車利活用市場の成長率は、車両販売(新車・中古車)の成長率よりも高いと言われている。
自動車保有を軸としたバリューチェーンがまだ形成されていないからこそ、日本やタイのような既存の自動車プレイヤーからの抵抗もない。ゆえにカンボジアでは、自動車利活用社会へと一気に進む可能性も否定できない。
デジタル通過「バコン」の存在
そして、それを後押しするもう一つの要素がカンボジアのデジタル通貨「バコン」だ。
元々、カンボジアでは自国通貨「リエル」ではなく、米国ドルが広く流通していた。この状況を打破するという目的もあり、カンボジア中央銀行はデジタル通貨の導入を決断した。
中央銀行によるデジタル決済の実用化は、バハマに次ぐ先進事例だ。デジタル決済と自動車利活用のトランザクションは、一般的に相性が良い。
日常的に少額を支払って自動車をシェアしたり、サブスクリプションで自動的に決済したりする場面においては、現金よりもデジタル決済が適している。バコンの普及が進むということは、自動車利活用の裾野が拡がるということでもある。
このように、カンボジアの自動車産業は従来型の構造が成立していないがゆえ、リープフロッグ的な進化を遂げる可能性は充分にあるだろう。
今回提示したシナリオは両極端なものであるが、どちらもあり得る姿だと考える。
関連企業においては、これからの動向をモニタリングしながら、どちらのシナリオに振れても柔軟に軌道修正が取れる体制を整えておくことが必要だろう。

-
Roland Berger下村 健一
一橋大学卒業後、米国系コンサルティングファーム等を経て、現在は欧州最大の戦略系コンサルティングファームであるローランド・ベルガーのアジアジャパンデスク統括に在籍(バンコク在住)。ASEAN全域で、消費財、小売・流通、自動車、商社、PEファンド等を中心に、グローバル戦略、ポートフォリオ戦略、M&A、デジタライゼーション、企業再生等、幅広いテーマでの支援に従事している。

-
TEL:+66 95 787 5835(下村)
Mail:kenichi.shimomura@rolandberger.com
17th Floor, Sathorn Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, 10500 | Bangkok | Thailand
\こちらも合わせて読みたい/
- この記事の掲載号をPDFでダウンロード
メールアドレスを入力後、ダウンロードボタンをクリックください。
PDFのリンクを送信いたします。
人気記事
アクセスランキング
新着ニュース
バックナンバーを探す
キーワードから探す
イベントカレンダー

タイ・ASEANの今がわかるビジネス経済情報誌