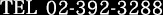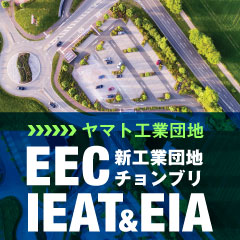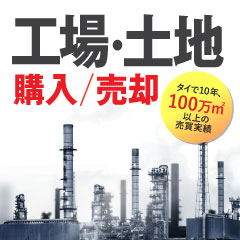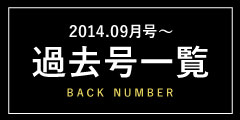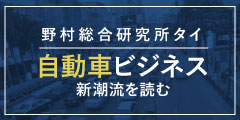だがある調査では、コロナ前に予測されていた2025年の東南アジアEコマース市場規模が21年中に到達するとされ、かなり前倒しでEコマース市場の拡大が進むことは間違いない。この状況を受けて、特に消費財メーカー等では自社のEコマース戦略を推進させようとお声掛けを頂くことが多い。
本稿では、このEコマースについて、少し一般的な観点とは異なる見方で論じたい。
コスト構造を変え得るEコマース
Eコマースを語る文脈でO2O(Online-To-Offline)は頻繁に登場する重要な考え方である。Eコマースは単に「オンラインでモノを売る」だけのチャネルではない。オフライン(実店舗)も含めてどのようなカスタマージャーニーを創るか、どういったブランドの世界観を構築するか、このような販売戦略上の重要論点に応えるために不可欠な要素となっている。
こういった観点でのEコマースの在り方は様々な文献や記事でも紹介されている。O2Oの重要性は当然ながら否定するものでもなく、むしろ大いに認めるところである。だが、その観点でのEコマースの詳細は他へ譲り、ここではコスト観点での意義に触れたい。 Eコマースは、流通コストの在り方を大きく変え得る戦略だ。特に、東南アジアではEコマースによるコスト貢献は先進国と比べて実は大きいと考える。

2025年の東南アジアEコマース市場規模が21年中に到達するという
東南アジアでは、物流インフラが先進国のそれと比較して脆弱である。また、伝統的小売などの小規模・零細商店がいまだリテールで重要な役割を担う状況下、自社で流通機能を持とうとすると巨額の固定費を抱えることになる。一方で、外部のディストリビューターや代理店に任せる場合は、適正な手数料(マージン)を把握しづらく、交渉やトラブル対応に要する時間(コスト)も想定以上にかかる。
これらのコストを、Eコマースは合理化できる余地がある。実際、ある消費財メーカーではEコマース戦略を正しく遂行することで、流通コストを30%削減することができたという。
自社の流通コスト構造を抑えたうえでのEコマース戦略
Eコマース戦略を検討するにあたって、その前提として自社の流通構造をしっかりと「見える化」する必要がある。どういったディストリビューターにどういった商品をどういったボリュームで流通させているか。それらディストリビューターがどういった小売店に卸しているか。小売店での売れ行きはどうか。どういった消費者がどの商品を買ってくれているか。そして、この状況を地域別に抑える。バンコクでは、チェンマイ等の地方都市ではどうか。
東南アジアではこういった流通構造を、自社のものですら定量的に抑えることは容易ではない。基本的には、ディストリビューター以降の流通はブラックボックスとなりがちだ。メーカーにとってみれば、実際にどういった小売店でどういった消費者に売られているかがわからない。
メーカーが小売と直接取引する場合でも、小売サイドがPOS(販売時点情報管理)を開示してくれないケースが多い。伝統的小売はより悩ましい状況だ。彼ら自身が大型スーパー等の他小売店から調達する場合も普通にある。また、ディストリビューターが小売ではなく、他のディストリビューターに転売することもある。
この多層的、かつ複雑な流通について、単に構造を把握するだけではない。コスト情報も見えるようにしなければならないのだ。「この流通ルートには、消費者に届くまでの一個あたり総流通コスト(マージン)が〇〇バーツかかっている。
その総流通コスト(マージン)の内訳は、一次ディストリビューターに対して〇〇バーツ、二次ディストリビューターには〇〇バーツ…値引きについては…」といった解像度で見えなければならない。
これらが見えたうえで、どの商品をどういったEコマースチャネルで流通させるかを判断する。その判断基準は、単にEコマースで想定される売上だけではない。
コスト最適化の観点を加え、Eコマースを用いてどう流通構造を組み直すかを検討していく。例えば、ある地方都市では流通コストに対して販売が芳しくないのであれば、Eコマースに委ねる可能性があるかもしれない。
ある商品は他メーカーとの棚取り争いが激しく、値引きも嵩むし店頭販促も相応に負担だ。であれば、今よりも低コストで同等以上の販売量をEコマースで目指せないか。また、無数にある伝統的小売をフォローする営業部隊を自社で持つ固定費負担は大きい。

インドネシアのECユニコーン企業「Bukalapak」
例えば、インドネシアのECユニコーン企業「Bukalapak」のようにB2BでEコマースをうまく活用して、伝統的小売にオンラインでメーカーに直接発注してもらえないだろうか。もちろん、それで営業部隊をゼロにはできないが、少なくとも抑制はできるはずだ。さらには、相応の事業規模があるのなら自社でEコマースプラットフォームを持つことも可能性としてはある。
最後に
このようにコスト観点でEコマースを見ていけば、何を検討すればいいかが少しわかりやすくなるのではないだろうか。販売は正直、水モノの側面もある。だが、コスト施策はしっかりとした分析がベースにあれば確度高く効果を得られる。
さらに言えば、その結果浮いたコストを原資に、これまでより大きいマーケティング投資が可能となる。日系消費財メーカーはマーケティングや販促にかける費用が小さすぎると言われがちだ。しかし、Eコマースをコスト面までの重層的な戦略として捉えることで、結果的にマーケティングといった販売面にも繋がる。
是非、短絡的なものではなく、多面的に見据えたEコマース戦略を構築していって欲しい。

-
Roland Berger下村 健一
一橋大学卒業後、米国系コンサルティングファーム等を経て、現在は欧州最大の戦略系コンサルティングファームであるローランド・ベルガーのASEANリージョンに在籍(バンコク在住)。ASEAN全域で、消費財、小売・流通、自動車、商社、PEファンド等を中心に、グローバル戦略、ポートフォリオ戦略、M&A、デジタライゼーション、企業再生等、幅広いテーマでの支援に従事している。

-
TEL:+66 95 787 5835(下村)Mail:kenichi.shimomura@rolandberger.com
17th Floor, Sathorn Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, 10500 | Bangkok | Thailand
\こちらも合わせて読みたい/

ダウンロードができない場合は、お手数ですが matsuoka@mediator.co.th までご連絡ください。
※入力いただいたメールアドレス宛に、次回配信分から定期ニュースレターを自動でお送りしております(解除可能)